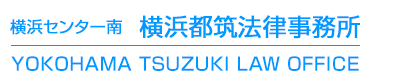足②偽関節・長管骨変形・脚長差の後遺障害等級
偽関節の後遺障害等級
下肢の偽関節は、骨折の癒合不全が残った箇所によって認定され、常に硬性補装具を必要とするかどうかで等級が分類されています。
その後遺障害の等級と認定基準は以下のとおりです。
| 1下肢に偽関節を残し、 著しい運動障害を残す |
7級10号 |
| 1下肢に偽関節を残す | 8級9号 |
7級「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」
「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合とされています。
a 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。
b 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。
c 脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残す。
8級「偽関節を残す」
「偽関節を残す」とは、次のいずれかに該当する場合とされています(常に硬性補装具を必要とするものではない場合ということになります)。
a 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、上記7級以外。
b 脛骨及び腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、上記7級以外。
c 脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、上記7級以外。
長管骨変形の後遺障害等級
長管骨とは、四肢を形づくる管状の骨で、下肢の長管骨は大腿骨・脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)です。
長管骨変形の後遺障害等級と認定基準は、以下のとおりです。
| 長管骨に変形を残す | 12級8号 |
12級「長管骨に変形を残す」
「長管骨に変形を残す」とは、次のいずれかに該当する場合とされています。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合も含まれます。
a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合)以上。
- (a) 大腿骨に変形を残す。
(b) 脛骨に変形を残す。
なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する。
b 大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全又は腓骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残す。
c 大腿骨又は腓骨の骨端部のほとんどを欠損。
d 大腿骨又は腓骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少。
e 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合。
この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
- (a) 外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合にあっては股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと。
(b) X線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること。
なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わない。
〔関連ページ〕
後遺障害の認定理由
(足の骨折などの例)
脚長差の後遺障害等級
骨折の影響で、一方の下肢が短縮し、あるいは一方の下肢が長くなって、両脚の長さに差が生じる後遺障害です。
その後遺障害等級の認定基準は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを計測する方法(SMD)で健側の下肢と脚長差を比較するとされています。
| 1下肢を5㎝以上短縮した | 8級5号 |
| 1下肢が5㎝以上長くなった | 8級相当 |
| 1下肢を3㎝以上短縮した | 10級8号 |
| 1下肢が3㎝以上長くなった | 10級相当 |
| 1下肢を1㎝以上短縮した | 13級8号 |
| 1下肢が1㎝以上長くなった | 13級相当 |

このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)